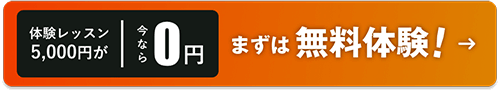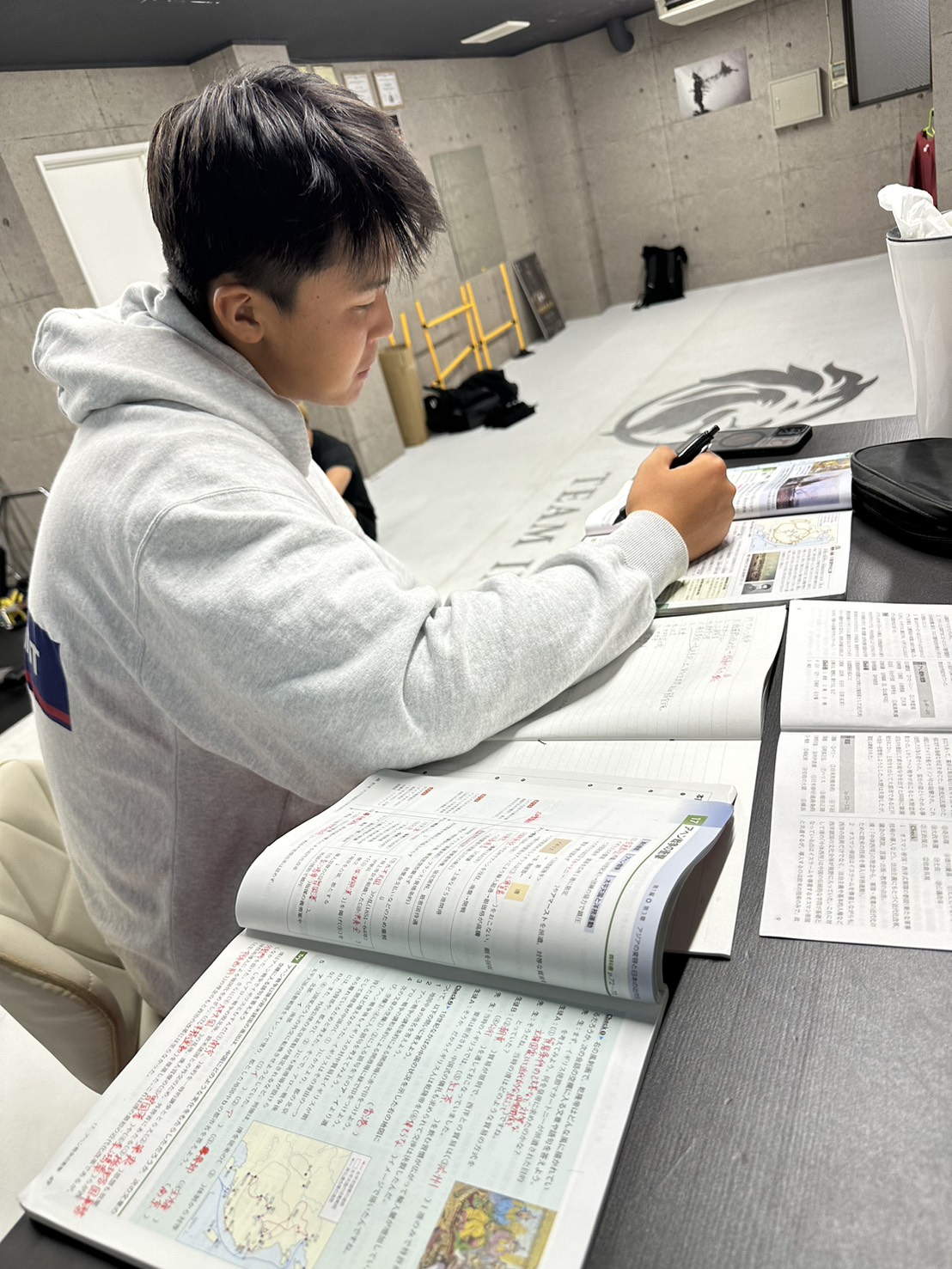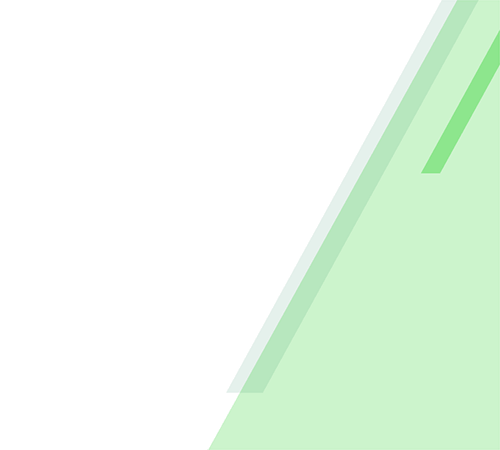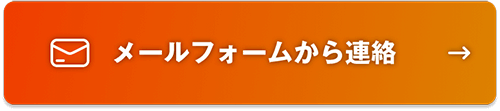こんにちは、船橋のパーソナルジム「FUNABASHI INSTITUTE(船橋 インスティチュート)」トレーナーの中田です。
今回は、学生のアスリートが FUNABASHI INSTITUTE でトレーニングに取り組む際、どのようなことをポイントに取り組んでいるか、そして実際にどのようなプログラムかをお伝えしていきます。
◇ 学生期は『土台作り』が基本
学生アスリートにとってのトレーニングというのは、短期的に結果を出すためだけでなく、将来を見据えて『身体の土台を作る』という考え方が重要であると考えています。
では、『身体の土台を作る』を具体的に挙げると…
・ケガをしにくい身体作り
・身体のサイズアップ、可動域、筋力>スピード、パワー
中高生の年代は成長期にあたり、骨や関節、筋肉が発達段階にあるため、過度な負荷や一時的な結果を追い求めるトレーニングは、ケガのリスクや将来の伸びしろを損なう可能性があります。
優先すべきは、目先の結果よりも長期的な身体の成長です。
◇ 基礎体力を整える重要性
競技特有のスキルや専門的な練習はもちろん必要ですが、それ以上に基礎的な体力要素をバランスよく鍛えることが優先されるべきです。
具体的には、柔軟性・全身の持久力・筋力・バランス感覚・ボディコントロールなどです。
トレーニングフォームを習得し、各関節の可動域や筋力を向上させることや、走る・跳ぶ・投げる などの基礎的な運動種目のクオリティを上げることは、本人の運動能力の向上に、そして結果的には競技力全体の底上げにつながります。
基礎体力を無視し、競技スキルのためのトレーニングに注力しすぎてしまうと、競技スキルの伸び悩みに直結してしまいがちです。
◇ ケガ予防とリカバリーの視点
学生アスリートは、部活やクラブチームでの練習も相当量こなしているので、オーバーユースによるケガを起こしやすいのも特徴です。
トレーニングだけでなく、休養や栄養も含めてコンディション管理を行うことが欠かせません。
特に、食事のバランスと睡眠の確保は、ケガの予防と回復に直結します。
栄養摂取の一つのトレーニングだと考えているので、何を・いつ・どのくらい摂取するのが良いのか、という具体的な食事の指導もさせていただきます。
では次に上記のポイントを踏まえ、実際にどのようなトレーニングを取り組んでいるのかをお伝えさせていただきます。
◇ 下半身のトレーニング
学生アスリートにとって下半身の強化は競技力の基盤です。
船橋 インスティチュートではまず…
①もも裏(ハムストリングス)の柔軟性を高める
②お尻の筋肉を正しく使う感覚を掴む
この2つの取り組みから始めます。
成長期の学生は特に前ももに負荷が集中しやすく、ハムストリングスや臀部が十分に機能していないケースが多いためです。
ヒップリフトやレッグカールなどの種目を通して「背面の筋肉を使う感覚」を養い、その上でスクワットやランジといった基本動作を取り入れていきます。
正しい関節の動かし方を覚える、かつ、出力を高めることで、走る・跳ぶ・切り返す、といった競技動作に活かされる体力を身につけます。
◇ 上半身背面のトレーニング
下半身のトレーニングの次に重視するのは「背中まわりの強化」です。
近年はスマートフォンやタブレットの長時間使用により、猫背気味の学生が非常に多く見られます。
姿勢が崩れたままでスポーツに取り組むと肩や腰に負担がかかり、パフォーマンスの低下やケガの原因にもなります。
そのため、船橋 インスティチュート では、押す動作やアームカールといった前面のトレーニングよりも、引く動作を優先して行います。
具体的には、チンニング(懸垂)、ロウイング、などの種目を実施し、肩甲骨の可動域を広げながら筋力を高めます。
背面を鍛えることで胸が自然に開き、呼吸がしやすくなることも大きなメリットです。
◇ リテラシーを高める
船橋 インスティチュート の特徴は、単にトレーニングを「やらせる」のではなく、学生アスリート自身に「課題は何か」を問いながら取り組んでもらう点にあります。
例えば「なぜ猫背になるのか?」「動き出しが遅いのはなぜか?」といった視点を持たせることで、トレーニングを考えながら取り組ませることが可能になります。
また、立ち姿勢の習慣や栄養摂取など、日常生活に直結する行動改善にも意識を向けてもらいます。
ジムでの1時間だけでなく、日常でどう身体を扱うかを考えることが、本当の意味での成長につながります。
知識と実践を結びつけることで、学生アスリートが自分で身体をマネジメントできる力を育むことを大切にしています。
いかがでしたでしょうか?
パーソナルジム FUNABASHI INSTITUTE では学生アスリートもトレーニングに取り組んでおります!
トレーニングジムをお探しの学生アスリートや保護者の皆さん、是非一度 パーソナルジム FUNABASHI INSTITUTE まで!
ご連絡お待ちしております。